ギャンブルをしてしまう人には、
以下のような特徴が見られます。


ギャンブルって魅力的!!
って、痛い目見る前に、、、。
参考にしてみて下さい!!
刺激追求傾向
「刺激追求傾向」とは、強い刺激や新しい体験を求める心理的な特徴のことを指します。
この傾向が強い人は、日常生活で感じる平凡さや退屈さに耐えられず、より刺激的でリスクの高い行動に引かれることが多いです。
ギャンブルを行う人にとって、この傾向は重要な要素となり、ギャンブル依存症の発展に寄与することがあります。
以下は、刺激追求傾向の詳細な掘り下げです。
1. 新奇性への欲求
刺激追求傾向が強い人は、新しい経験や未知の状況に対して強い興味を持ちます。ギャンブルでは、結果が予測できないスリルや、偶然性の高い結果に対する期待がこの新奇性の欲求を満たします。新しいカジノゲームや賭け方を試すことで、常に新鮮な刺激を求め続けます。
2. 高リスク行動への傾倒
リスクを伴う行動に対する恐れが少なく、むしろそのリスクから得られる刺激や興奮を好む傾向があります。ギャンブルでは大きな賭けをしたり、勝敗が予測できない状況に身を置くことが、日常生活では得られない強い感情的な高揚をもたらします。
3. 報酬系の敏感さ
脳の報酬系は、刺激や興奮を感じたときに活性化します。刺激追求傾向が強い人は、この報酬系が特に敏感で、ギャンブルのような行動によって強い快感を得ます。この快感を繰り返し求めることで、ギャンブルに依存するリスクが高まります。
4. 忍耐力の低さ
刺激追求傾向が強い人は、退屈や単調さに対する耐性が低く、すぐに興味を失ってしまいます。そのため、持続的な努力や忍耐を要する活動よりも、短期間で強い刺激を得られるギャンブルのような活動に傾倒しやすいです。
5. 社会的規範やリスクの軽視
刺激を追求するあまり、社会的な規範やリスクを無視することがあります。例えば、家族や友人の反対を押し切ってギャンブルを続けたり、金銭的な損失の可能性を軽視してしまうことがあります。これは、長期的な結果よりも、瞬間的な刺激や満足感を優先するためです。
6. 依存性への脆弱性
刺激追求傾向が強い人は、ギャンブルに限らず、アルコールや薬物など他の依存行動にも陥りやすいと言われています。これらの行動もまた、強い刺激や報酬を提供するため、同様のメカニズムで依存が形成されます。
このように、刺激追求傾向が強い人は、ギャンブルのスリルやリスクを楽しむあまり、制御が効かなくなりやすいです。
そのため、この傾向を持つ人は、自分自身を理解し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。

自己制御の低さ
「自己制御の低さ」とは、衝動や欲求を抑える能力が乏しいことを指します。
この特徴を持つ人は、短期的な快楽や満足感を求め、長期的な利益や目標を達成するために必要な努力を継続することが難しい傾向があります。
自己制御の低さは、ギャンブル行動において特に顕著に現れ、ギャンブル依存症のリスクを高める要因となります。
以下は、自己制御の低さについて詳しく掘り下げた内容です。
1. 衝動性
自己制御が低い人は、衝動的な行動をとりやすいです。衝動性とは、瞬間的な欲求に基づいて行動を起こし、結果や長期的な影響を考慮せずに即座に反応してしまう性質です。ギャンブルにおいては、突然の賭けや無計画な追加ベットがこれに該当します。衝動的な賭けは、予算や計画を無視することが多く、結果として大きな損失を招くことがあります。
2. 短期的快楽の優先
自己制御の低さは、短期的な快楽や満足感を優先する傾向にも表れます。ギャンブルでは、勝利の瞬間的な喜びや興奮が非常に強く、これを求めるあまり、長期的な経済的安定や人生の目標を犠牲にしてしまうことがあります。こうした短期的な満足感を求める行動は、繰り返されることで悪循環に陥りやすいです。
3. 計画性の欠如
自己制御が低い人は、長期的な計画を立てることや、その計画に従って行動することが苦手です。ギャンブルに関して言えば、予算を決めてそれを守ることが難しく、計画的なギャンブルができなくなります。計画性の欠如は、結果として過度なギャンブル行為や予想外の損失に繋がります。
4. 誘惑への脆弱性
自己制御が低いと、誘惑に対して非常に脆弱になります。たとえば、カジノやオンラインギャンブルの広告、他人の成功話など、ギャンブルを促進する要因に対して抵抗できず、すぐに影響を受けてしまいます。この脆弱性は、ギャンブルを始めるきっかけになりやすく、また一度始めたギャンブルを止めることも困難にします。
5. ストレスや感情に対する対処の弱さ
自己制御の低さは、ストレスやネガティブな感情への対処能力の低さとも関連しています。ストレスや不安、孤独感などを感じたときに、それを解消するためにギャンブルに走ることが多くなります。ギャンブルによる一時的な快感が、これらの感情を和らげる手段として用いられることで、依存が深まるリスクがあります。
6. 反復行動の強化
自己制御が低い人は、一度行った行動を繰り返す傾向が強くなります。ギャンブルのような強い報酬を伴う行動は、自己制御が弱いと繰り返されやすく、習慣化されてしまいます。この習慣化は、ギャンブル行動をさらにエスカレートさせる要因となり、依存症へと発展する可能性があります。
7. 結果を無視した行動
自己制御が低い人は、目の前の欲求に集中しすぎて、行動の結果やリスクを無視してしまうことがあります。たとえば、大きな損失を出しても「次は勝てるかもしれない」という希望的観測でギャンブルを続け、さらに深みにはまっていくことがあります。
このように、自己制御の低さはギャンブル行動を助長し、依存症のリスクを高める重要な要因です。
自己制御を強化するためには、衝動をコントロールするスキルや、長期的な視野を持つことが求められます。
また、環境や人間関係を見直し、誘惑から遠ざかることも有効です。
勝利への執着
「勝利への執着」とは、一度の勝利や成功体験が強く印象に残り、その後も勝ち続けたい、あるいは失ったものを取り戻したいという強い欲望を抱く心理的傾向を指します。
この傾向は、ギャンブル行動において非常に影響力があり、特にギャンブル依存症に陥るリスクを高める要因となります。
以下は、勝利への執着について詳しく掘り下げた説明です。
1. ポジティブな強化
勝利への執着は、ポジティブな強化の一形態です。ギャンブルで勝利を経験すると、脳の報酬系が活性化され、強い快感や満足感が得られます。この経験が脳に刻まれることで、再び同じ快感を求めるようになります。勝利の記憶が鮮明であればあるほど、再度ギャンブルに挑む動機が強化されます。
2. 「もう一度勝てる」という信念
勝利への執着が強い人は、「もう一度勝てる」という信念を持ち続けることが多いです。たとえ連続して負けが続いたとしても、過去の勝利経験が頭に残り、再度の勝利を信じてギャンブルを続ける傾向があります。この信念が、さらなる賭けを引き起こし、結果として損失が膨らむことがしばしばあります。
3. 損失回復への強い欲求
勝利への執着は、損失回復への強い欲求とも密接に関連しています。ギャンブルで負けた際に、「失った分を取り戻したい」という強い欲望が生まれます。この欲望は、さらに多くのリスクを取る行動につながり、負の連鎖を引き起こすことがあります。損失を取り戻すためにさらに大きな賭けを行うことで、依存が深まりやすくなります。
4. 勝利の過大評価
勝利への執着が強い人は、勝利の価値や重要性を過大評価する傾向があります。実際の勝率やリスクを冷静に評価することが難しくなり、ギャンブルで得た一時的な勝利に過剰な意味を見出します。これにより、ギャンブルを続けることが「正しい選択」であると誤って認識するようになります。
5. 自己評価の変動
勝利への執着は、自己評価にも影響を与えます。ギャンブルで勝利すると、自己評価が一時的に高まるため、自己肯定感を得る手段としてギャンブルに依存することがあります。一方で、負けると自己評価が低下し、再度の勝利を求めてギャンブルを続けるという悪循環に陥る可能性があります。
6. 「次は勝つ」への思い込み
ギャンブル依存に陥る人は、たとえ負けが続いても「次こそ勝てる」という思い込みを持つことが多いです。この思い込みは、過去の勝利経験や運に対する過信から生じることがあります。このような考え方は、理性的な判断を妨げ、リスクの高い賭けを続ける要因となります。
7. 感情的な揺さぶり
勝利への執着は、強い感情的な揺さぶりを伴うことがあります。勝った時の高揚感や負けた時の悔しさが混ざり合い、ギャンブル行動をさらに強化します。感情の揺れが大きいほど、冷静な判断が難しくなり、結果として依存症のリスクが高まります。
8. 社会的・経済的なプレッシャー
勝利への執着は、社会的や経済的なプレッシャーとも結びつくことがあります。たとえば、周囲からの期待や経済的な困難があると、ギャンブルでの勝利によってそれらの問題を解決しようとする傾向が強まります。このようなプレッシャーがある場合、ギャンブル行動がより頻繁かつリスクの高いものになる可能性があります。
勝利への執着は、ギャンブル行動を強く推進する心理的な要因です。
この執着を克服するためには、過去の勝利経験に囚われず、冷静に現実を直視することが重要です。
また、ギャンブル行動が自分に与える影響を理解し、専門家の支援を受けることも重要です。
逃避行動
「逃避行動」とは、現実の問題やストレスから逃れるために、他の行動や思考に逃避することを指します。
ギャンブルは、こうした逃避行動の一つとして機能しやすく、特に現実の困難や感情的な苦痛から逃れる手段として利用されることが多いです。
逃避行動は、短期的には一時的な安らぎを提供するものの、長期的には問題を悪化させることが多く、ギャンブル依存症の発展に寄与する可能性があります。
以下は、逃避行動について詳しく掘り下げた説明です。
1. 現実逃避のメカニズム
逃避行動は、現実の問題や感情的な苦痛に直面することを避けるためのメカニズムです。ギャンブルは、その瞬間だけでもストレスや悩みを忘れさせてくれる強力なツールとして機能します。賭けのスリルや勝敗の結果に集中することで、日常の問題や感情を一時的に忘れることができるため、現実逃避の手段として利用されやすいです。
2. ストレスや不安からの逃避
逃避行動は、特にストレスや不安を感じているときに顕著になります。仕事や人間関係の問題、経済的な困難などから逃れたいという思いが強いと、ギャンブルに依存するリスクが高まります。ギャンブルをすることで一時的にストレスが軽減されるため、その行動が習慣化し、依存症に陥る可能性があります。
3. 感情の処理能力の低下
逃避行動に頼る人は、感情を適切に処理する能力が低下していることが多いです。感情的な痛みや不安に対処する代わりに、ギャンブルを通じてそれらを抑え込もうとします。このような行動が続くと、感情の処理能力がさらに低下し、問題が悪化していく悪循環に陥る可能性があります。
4. 自己認識の回避
逃避行動は、自己認識や自己評価に直面することを避ける手段でもあります。自分の問題や欠点に向き合うことが難しいと感じる人は、ギャンブルなどの逃避行動を通じて、自分自身を見つめることを避けようとします。この結果、自己改善や問題解決が遅れ、人生の課題が積み重なってしまうことがあります。
5. 快楽の追求
逃避行動は、快楽を追求することでネガティブな感情を打ち消す試みでもあります。ギャンブルでは、勝利やスリルから得られる一時的な快楽が現実の問題を覆い隠し、その瞬間だけでも「幸せ」を感じることができます。しかし、この快楽は一時的なものであり、持続的な解決にはならないため、さらなる逃避行動を誘発します。
6. 問題の先送り
逃避行動に頼る人は、問題を直視することを避け、先送りにする傾向があります。ギャンブルにのめり込むことで、現実の問題を解決するための行動を取る時間やエネルギーが奪われ、結果として問題がさらに悪化することがあります。逃避行動によって問題が解決されないことを理解していながらも、現実に直面することの恐怖や不安から逃れるために、その行動を続けてしまうことが多いです。
7. 自己破壊的な行動
逃避行動は、自己破壊的な行動に繋がることがあります。ギャンブルは、その代表的な例で、逃避を求めるあまり、自分の財産や人間関係を損なう結果になることが少なくありません。短期的な快楽を追求することで、長期的な損害を被ることになるため、自己破壊的な悪循環が形成されます。
8. 社会的孤立のリスク
逃避行動としてギャンブルに依存することで、社会的な孤立が進むリスクもあります。ギャンブルに時間やお金を費やすことで、家族や友人との関係が疎遠になり、孤独感が深まります。この孤独感がさらにギャンブルへの依存を強めるという悪循環が生まれることがあります。
9. 短期的な解決策の選択
逃避行動をとる人は、長期的な問題解決よりも短期的な解決策を選びがちです。ギャンブルは、その一例であり、瞬間的な逃避と快楽を提供するため、長期的なストレスや問題の解決を先送りにしてしまいます。しかし、長期的には問題が蓄積し、解決がより困難になることが多いです。
10. 依存症への進展
逃避行動が続くと、ギャンブル依存症に発展するリスクが高まります。依存症に陥ると、逃避行動がますます強化され、現実逃避のためにさらに多くの時間や資金をギャンブルに費やすことになります。これは、自己破壊的な行動のサイクルを強化し、最終的には個人の生活全般に深刻な悪影響を及ぼすことになります。
逃避行動は、現実の問題から一時的に逃れるための行動ですが、その結果として新たな問題を生み出すことが多いです。
ギャンブルを通じた逃避行動は、特に危険性が高く、依存症や社会的孤立、経済的破綻など深刻な影響をもたらすことがあります。
このような行動パターンを認識し、適切な対策を講じることが重要です。
たとえば、ストレスや不安に対処するための健全な方法を学び、必要に応じて専門家のサポートを受けることが効果的です。
財政管理の甘さ
「財政管理の甘さ」とは、個人が自分の収入や支出、貯蓄などを効果的に管理する能力が不足している状態を指します。
ギャンブルにおいては、この財政管理の甘さが、予算を超えた無謀な賭けや、経済的な問題を引き起こすリスクを高める要因となります。
以下は、財政管理の甘さについて詳しく掘り下げた説明です。
1. 予算の欠如
財政管理が甘い人は、明確な予算を設定しないことが多いです。たとえば、ギャンブルに使う金額を事前に決めておかず、その場の感情や衝動に任せて賭け金を増やしてしまいます。これは、計画的な資金管理ができていないことを示し、結果として必要以上の出費を招きます。
2. 支出の優先順位の誤り
財政管理が甘いと、支出の優先順位を正しく設定できません。生活費や貯蓄、借金返済など、必要な支出を後回しにしてギャンブルにお金を使うことが多くなります。これにより、日常生活に必要な支出が圧迫され、生活の質が低下することがあります。
3. 衝動的な支出
財政管理が甘い人は、衝動的な支出に対して脆弱です。ギャンブルにおいては、勝ち負けに関わらず、その場の感情に任せて賭け金を増やしたり、連続して賭けを行ったりする傾向があります。このような衝動的な支出は、計画的な資金管理を妨げ、結果として大きな損失を招くことになります。
4. 貯蓄習慣の欠如
財政管理が甘いと、貯蓄の習慣が欠如していることが多いです。ギャンブルに多額のお金を使ってしまうため、貯蓄に回す余裕がなくなります。これは、将来の経済的な安定を脅かし、予期せぬ支出や緊急時に対応できなくなるリスクを高めます。
5. 借金のリスク
財政管理が甘いと、借金をしてまでギャンブルを続けるリスクがあります。手元の現金がなくなった際に、クレジットカードや消費者金融から借金をしてギャンブルを続けることが多くなり、これが深刻な経済的問題を引き起こす原因となります。借金が増えることで、返済の負担が大きくなり、さらなるギャンブルに依存する悪循環に陥る可能性があります。
6. 現実逃避としての支出
財政管理が甘い人は、現実逃避としてお金を使うことがあります。ストレスや不安を感じたときに、ギャンブルで一時的な解放感を得ようとして、計画外の支出をしてしまうことがあります。このような支出は短期的な満足感を得るためのものであり、長期的には財政状況を悪化させることになります。
7. リスク管理の欠如
財政管理が甘い人は、リスク管理の意識が低いことが多いです。ギャンブルにおいて、負けた場合のリスクを十分に考慮せず、過度な賭けを行うことが一般的です。結果として、計画外の大きな損失を被る可能性が高まり、経済的な安定が脅かされます。
8. 家計全体への影響
財政管理が甘いと、ギャンブルにかかる費用が家計全体に深刻な影響を与えることがあります。家族やパートナーとの共有資産や貯蓄が減少し、生活費が圧迫されることで、家庭内のトラブルやストレスの原因となることがあります。財政的な問題が家族関係にも悪影響を及ぼすことは少なくありません。
9. 長期的視点の欠如
財政管理が甘い人は、短期的な欲望に目を向けがちで、長期的な視点を持つことが難しいです。ギャンブルによる即時的な報酬を求めるあまり、将来的な経済的安定や目標達成のための資金管理が疎かになります。この結果、老後の生活や子供の教育資金など、長期的な財政目標が達成できなくなるリスクがあります。
10. 回復の難しさ
財政管理が甘い人が一度大きな経済的損失を被ると、その回復が非常に難しくなります。ギャンブルによる損失を取り戻そうとさらにギャンブルに依存することが多く、これがさらに財政状況を悪化させる原因となります。このような悪循環から抜け出すためには、強い意志と計画的な財政管理が必要ですが、それができないために問題が深刻化することがあります。
財政管理の甘さは、ギャンブル依存に直結するリスクが高く、個人の経済的安定を大きく揺るがす要因となります。
これを防ぐためには、予算を明確に設定し、支出の優先順位を理解し、貯蓄の習慣を身につけることが重要です。
また、リスク管理の意識を高め、借金や衝動的な支出を避けるための具体的な対策を講じることも必要です。
改善方法
ギャンブルをしてしまう人の特徴に対して、それぞれに合った改善方法を提案します。
これらの方法は、ギャンブル行動をコントロールし、依存を防ぐための実践的なアプローチです。
1. 刺激追求傾向の改善方法
- 代替活動の導入
ギャンブル以外で興奮やスリルを感じられる健康的な趣味や活動を見つけることが重要です。例えば、スポーツや冒険活動、クリエイティブな趣味(アート、音楽など)を取り入れることで、刺激を健全な形で追求できます。 - リスク管理教育
リスクの捉え方や管理方法を学び、リスクのある行動を適切に評価するスキルを養うことで、過剰な刺激追求行動を抑制します。
2. 自己制御の低さの改善方法
- 自己制御訓練
マインドフルネスや瞑想、呼吸法などの自己制御を高めるテクニックを取り入れることで、衝動に対処しやすくなります。日々の生活でこれらの技法を実践することで、ギャンブルの衝動をコントロールする力を強化します。 - 具体的な目標設定
ギャンブルに関する具体的なルール(例: 1週間に使う金額の上限を設定する)を設定し、それを守る練習を重ねることで、自己制御能力を高めます。
3. 勝利への執着の改善方法
- 勝率とリスクの再評価
ギャンブルの現実的な勝率やリスクを正確に理解するための教育を受けることで、勝利への過度な執着を減少させます。期待値の計算や、長期的な損益を理解することで、ギャンブルへの認識を冷静なものに変えます。 - 過去の勝利の再評価
過去の勝利や損失を感情的に捉えるのではなく、客観的に分析することで、勝利への執着を和らげます。日記をつけて、自分のギャンブル行動とその結果を記録することも有効です。
4. 逃避行動の改善方法
- ストレス管理技術の習得
ストレスや不安に対処するための健康的な方法を学びます。カウンセリングやストレス管理のワークショップに参加することで、ギャンブル以外のストレス解消法を身につけます。 - 問題解決スキルの強化
直面している問題を逃げずに解決するスキルを身につけることが重要です。時間管理、コミュニケーション技術、問題解決のフレームワークなどを学び、現実的な対応策を実践します。
5. 財政管理の甘さの改善方法
- 予算管理の訓練
家計簿をつけたり、ファイナンシャルプランナーの指導を受けることで、収入と支出のバランスを管理するスキルを向上させます。ギャンブル用の予算を厳格に設定し、それを超えないようにする習慣をつけます。 - 貯蓄の習慣化
貯蓄の重要性を理解し、毎月の収入の一定割合を貯蓄に回す習慣を身につけます。また、緊急時のための予備資金を設けることも推奨されます。 - 借金のリスクを避ける
借金をしてまでギャンブルを続けないよう、クレジットカードや借入れの利用を制限し、財政的な破綻を防ぎます。
これらの改善方法を実践することで、ギャンブル行動をコントロールし、長期的な依存を防ぐことが可能です。
必要に応じて、専門家の支援を受けることも考慮に入れるとよいでしょう。
ギャンブルをしない人の特徴
「ギャンブルをしない人」には、以下のような特徴が見られます。
これらの特徴は、ギャンブルに対する興味や依存を抑えるのに役立つ要因となります。
1. 自己制御が強い
ギャンブルをしない人は、自己制御力が強く、衝動的な行動を抑えることができます。自分の欲望や衝動に流されず、冷静に物事を判断し、計画に従って行動する傾向があります。
2. リスク回避志向が強い
ギャンブルをしない人は、リスクに対する感受性が高く、不確実性の高い行動を避ける傾向があります。彼らはリスクを慎重に評価し、無駄なリスクを冒さないようにするため、ギャンブルには手を出しません。
3. 現実的な金銭感覚を持っている
金銭管理がしっかりしており、お金の使い方に対する計画性があります。収入と支出をバランスよく管理し、無駄遣いや不必要なリスクを避けるため、ギャンブルに使うお金がないと判断します。
4. 長期的視点を持っている
ギャンブルをしない人は、長期的な目標や将来の計画を大切にします。短期的な快楽や刺激よりも、長期的な安定や成功を優先するため、ギャンブルのような一時的な楽しみに惹かれることが少ないです。
5. 健全なストレス解消法を持っている
ストレスや不安を感じたとき、ギャンブルではなく、運動、趣味、友人や家族との時間など、健全な方法でストレスを解消します。これにより、感情的にギャンブルに頼る必要がなくなります。
6. 価値観や倫理観が明確
ギャンブルに対して否定的な価値観や倫理観を持っている人もいます。例えば、ギャンブルを不道徳な行為と考えたり、社会的な責任感からギャンブルを避けたりする人たちです。彼らは自己の価値観に基づいて行動し、ギャンブルをしない選択をします。
7. 社会的サポートが強い
家族や友人、コミュニティとの強い絆を持っている人は、孤独感やストレスを感じにくく、ギャンブルに頼る必要が少なくなります。また、周囲からのサポートがあることで、健全な行動を保つことができます。
8. 教育や知識が豊富
ギャンブルのリスクや依存症の問題について十分に理解している人は、その危険性を認識し、ギャンブルに手を出さない傾向があります。教育や知識があることで、ギャンブルの誘惑に対して強い抵抗力を持つことができます。
9. 代替的な楽しみを持っている
ギャンブル以外に楽しみや趣味を持っている人は、ギャンブルを必要としません。例えば、スポーツ、音楽、アート、旅行など、多様な活動に興味を持ち、それらを楽しむことで、ギャンブルへの依存を防ぐことができます。
10. 規律正しい生活習慣
規則正しい生活習慣を持っている人は、日常生活の中でギャンブルに関わる時間が少なくなります。計画的な日常生活を送ることで、ギャンブルに費やす余暇がなくなり、その誘惑から遠ざかることができます。
これらの特徴を持つ人は、ギャンブルのリスクに対して高い抵抗力を持ち、依存症になる可能性が低いと考えられます。
これらの特徴を身につけることで、ギャンブルから距離を置き、健全な生活を送ることが可能です。
まとめ
- 刺激追求傾向
ギャンブルに伴うリスクやスリルを楽しむ傾向があります。常に刺激や興奮を求める性格の人は、ギャンブルによる高揚感を求めがちです。 - 自己制御の低さ
自分の行動や衝動を抑えることが苦手で、一度ギャンブルを始めるとやめられなくなることがあります。衝動的にお金を賭けることが多いです。 - 勝利への執着
一度の勝利や損失をきっかけに、もっと勝ちたい、損失を取り戻したいという強い欲求が生まれ、ギャンブルを続ける原因となります。 - 逃避行動
ストレスや現実から逃れたいという思いから、ギャンブルにのめり込むことがあります。問題を抱えている人ほど、ギャンブルに依存する傾向があります。 - 財政管理の甘さ
お金に対する計画性が乏しく、負けてもお金を使い続けてしまうことがあります。財政的な責任感が低く、無計画に資金を賭けてしまうことが特徴です。
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 刺激追求傾向 | リスクやスリルを楽しむ傾向があり、常に刺激や興奮を求める性格の人は、ギャンブルによる高揚感を求めがちです。 |
| 自己制御の低さ | 衝動的な行動を抑えることが苦手で、一度ギャンブルを始めるとやめられなくなることがあります。 |
| 勝利への執着 | 一度の勝利や損失をきっかけに、もっと勝ちたい、損失を取り戻したいという強い欲求が生まれ、ギャンブルを続ける原因となります。 |
| 逃避行動 | ストレスや現実から逃れるためにギャンブルにのめり込むことがあり、問題を抱えている人ほど依存しやすいです。 |
| 財政管理の甘さ | お金に対する計画性が乏しく、負けてもお金を使い続けてしまい、無計画に資金を賭けることがあります。 |
これらの特徴を持つ人は、ギャンブルのリスクに対して特に注意が必要です。

自分の感情が制御出来なくなるまでやらない事!!
これにつきますね!気をつけて!!
※相違している部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。










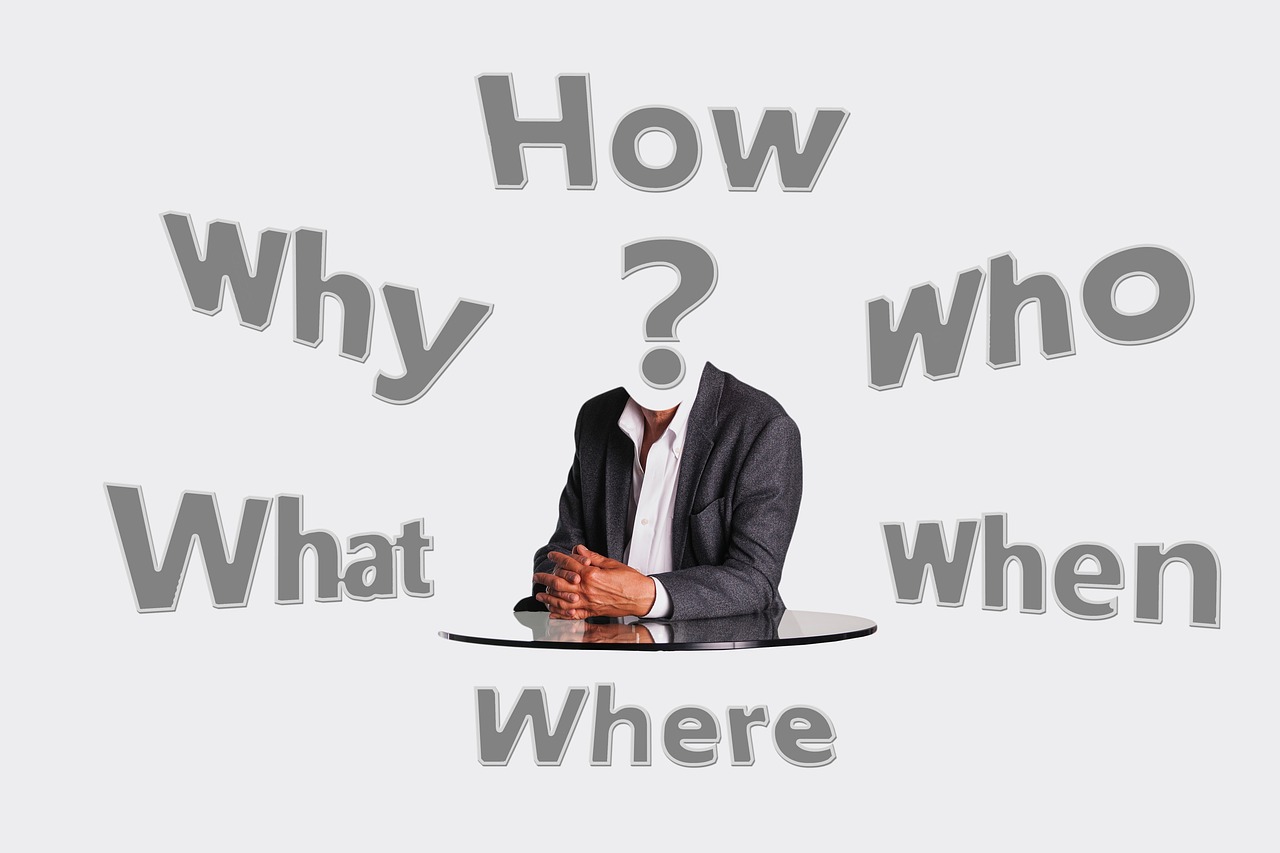






コメント